池鯉鮒
山町
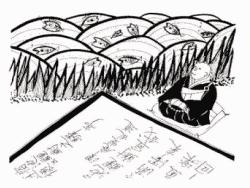
おおむかし、ちりゅうは知立・智立などと書いていました。江戸に幕府ができると、東海道は一番重要な道路とされ、五十三次の宿場ができて、知立は江戸から三十九番目の宿となって、「池鯉鮒」と書くようになりました。
「ちりふの町の右の方に長き池(御手洗池)あり。神の池なり。鯉・鮒多し。依って、名とす。しかれども、和名抄に碧海郡智立とあり」(吾嬬路より)
御手洗池は殺生禁断(生きものを殺してはいけない)の池で鯉、鮒が多く、「池鯉鮒」と書くようになったのです。この池の水で、知立神社のお祭りには体を清めたり、おみこしを洗いました。日照りが続くと雨ごいの神事も行われました。また、宿場の北側の広い田んぼの水にも使いました。
ある時、中町の称念寺にりっぱなお坊さんが泊まりました。
「すみませんが、お泊まりくださった記念に何か書いていただきたいのですが。」
と、和尚さんが遠慮しながらお願いしますと、
「ああ、いいとも、いいとも。」
と、そのお坊さんは、心よく引き受けてくださって、小僧さんが墨をすっている間に、
「池鯉鮒の宿の松並木も、御手洗池もよく手入れがしてあって美しい。わたしは、みなさんのこの自然を大切にする心が好きで、ここに泊めてもらったのだよ。」
とおっしゃいました。そして、畳一枚もある大きな紙に、漢詩と和歌を書いてくださいました。
宿池鯉鮒之驛亭
述懐云
沢庵叟乱道
里名池鯉鮒宜哉
春水洋々満澤来
非是魚争識魚楽
搖頭擺尾日千回
みなそこのうろくず
までも
君が代にあるや
うれしき
池の鯉鮒
寛永廿一年暮春十七日
沢庵禅師のこの詩碑は、池の一部を埋めて作った御手洗児童公園の中に、昭和四十三年四月三日に建立されました。
公園の南側には、池の名残の御手洗川がすがすがしく流れています。
おしまい
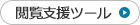








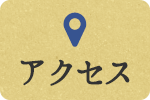
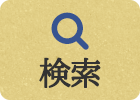
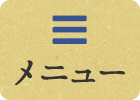

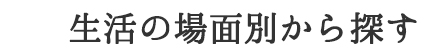








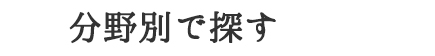
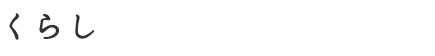


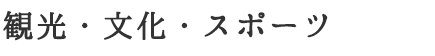


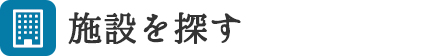
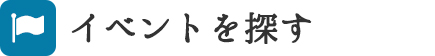
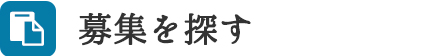
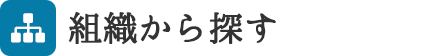
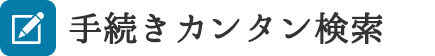
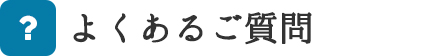
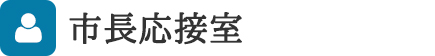

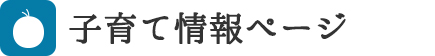
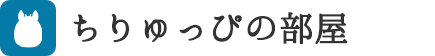
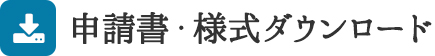

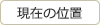

更新日:2023年08月23日