知立市の個人情報保護制度
1.個人情報保護制度とは
個人情報を適正に取り扱うとともに、市の機関が保有する自己に関する個人情報の開示及び訂正等を請求する個人の権利利益を保護する制度です。
2.個人情報とは
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真等により特定の個人を識別できるものをいいます。これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。
3.この制度を実施する実施機関
市長
議会
教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
水道事業管理者の権限を行う市長
4.開示、訂正、消去、利用の停止又は提供の停止請求について
自分に関する個人情報を自ら管理できる権利として、実施機関が保有している個人情報について、開示、訂正、消去、利用の停止又は提供の停止を請求することができます。
(1)開示請求
誰でも、自分に関する個人情報の開示を請求することができます。請求があった場合には、実施機関は、次に掲げる情報のいずれかが含まれているときを除き、個人情報を開示します。
ア 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある主務大臣、知事等の指示により、明らかに開示することができないと認められる情報
イ 開示請求者以外の者に関する個人情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの。
ウ 事業者に関する情報であって、開示することにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
エ 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
オ 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
カ 代理人により開示請求がなされた場合において、開示することが本人の利益に反すると認められる情報
(2)訂正、消去、利用の停止又は提供の停止請求
誰でも、開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思われるとき、実施機関が違反して収集したり、利用又は提供していると思われるときは、実施機関に対し、訂正、消去、利用の停止又は提供の停止請求をすることができます。
5.開示請求の手続きについて
(1)請求の方法
個人情報を開示請求するときは、開示請求に係る個人情報を特定し、個人情報開示請求書を主管課へ提出していただきます。なお、請求に際しては、運転免許証、旅券等本人であることを確認できる書類の提出又は提示が必要となります。
(2)開示・不開示の決定
開示請求を受け付けた日から14日以内に開示するかどうか決定をして、その結果を文書でお知らせします。なお、14日以内に決定できない場合は、延長する理由と期間を文書でお知らせします。
(3)開示の方法
個人情報開示決定通知書が届いた後、その通知書をお持ちになって、お知らせした日時・場所にお越しいただきます。
(4)費用の負担
公文書の閲覧は無料です。公文書の写しを交付する場合は、その実費相当額の負担を求めます。
(A3判以内1枚10円、カラーコピーの場合は1枚50円)
6.訂正の決定について
実施機関は、訂正、削除、利用の停止又は提供の停止があった個人情報について、30日以内に決定をし、その結果を文書で通知します。
なお、30日以内に決定できない場合には、30日以内の期間延長をしますが、延長後の期間とその理由を文書で通知します。
7.不服申立て
実施機関が行った決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は知立市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、再度、開示するかどうかの決定をします。
8.出資団体等の個人情報保護
実施機関は、知立市土地開発公社など市が出資を行うその他の団体に対して、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう、その指導に努めます。
9.罰則
(1)実施機関の職員(職員であった者)や受託事務の従事者(従事書であった者)が、正当な理由がないのに、個人の秘密を含み体系的に構成された電子的な公文書を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(2)実施機関の職員や受託事務の従事者が、その職務上知り得た個人情報で公文書に記録されているものを、不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(3)実施機関の職員が職権を濫用して、職務以外の目的で個人の秘密が記録された文書などを収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(4)偽りその他不正の手段によって、個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられます。
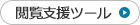








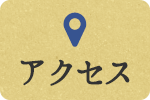
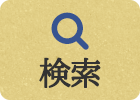
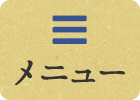

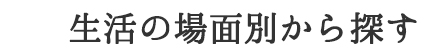








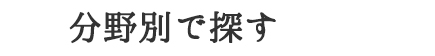
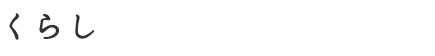


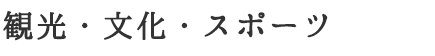


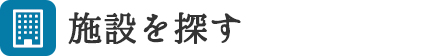
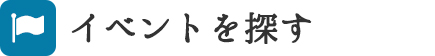
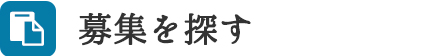
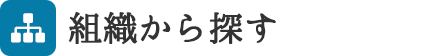
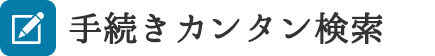
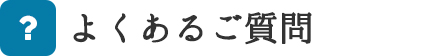
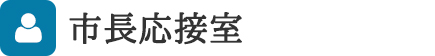

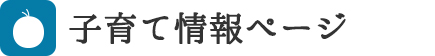
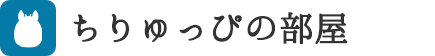
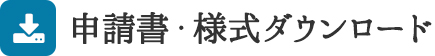

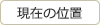

更新日:2024年08月15日