用語説明
財政力指数
財政力指数=基準財政収入額/基準財政需要額
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値です。通常は3か年平均が用いられます。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するもので、次の算式により算出されます。
標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等
基準財政需要額
普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政サービスを行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するもので、各行政項目ごとに、次の算式により算出されます。
単位費用 × 測定単位 × 補正係数
(測定単位1当たり費用) (人口・面積等) (寒冷補正等)
経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費等のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源収入)、減収補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額です。
各種財政指標の算定に用いられます。
積立金
財政運営を計画的にするため、年度間の財源調整や特定の目的のために積み立てるもので、地方自治法上は基金として処理されているものです。
地方債
道路・公園・下水道・学校などを整備するときに、国などから借り入れるお金、つまり「市の借金」です。
また、将来的に利益を受けることになる市民にも負担してもらい、世代間の公平を図る目的もあります。
実質公債費比率
健全化判断比率の一つで地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものです。
公債費負担比率
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合です。
公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表し、一般的には15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。
継続費
建設工事でその履行に数年度を要するものなどについては、予算において、その経費の総額と年割額を定め、数年度にわたって支出することができ、これを継続費といいます。
継続費は、毎会計年度の年割額の経費のうち、その年度内に支出が終わらなかったものは、その継続費の継続年度の終わりまで順次繰り越しして使用することができます。
繰越明許費
歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の理由によって、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算において繰越明許費として定め、翌年度に繰り越して使用することができます。
この場合において、経費を繰り越す場合は、そのために必要な財源も繰り越さなければなりません。繰越財源は、前年度の歳入によるのが原則ですが、国庫補助金や地方債の未収入金額については、その一部に充てることができます。
債務負担行為
歳出予算、継続費、繰越明許費によるものを除き、地方公共団体が契約の締結など債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておくことが必要です。
債務負担行為が必要な例:契約をする(=債務を負担する)年度の翌年度に支払いをする場合
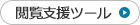








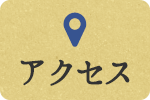
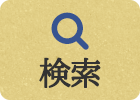
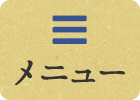

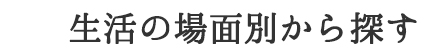








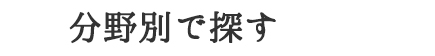
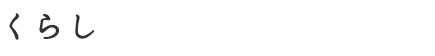


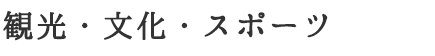


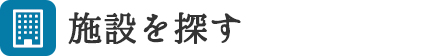
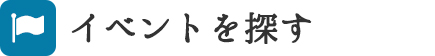
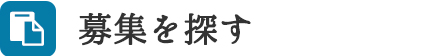
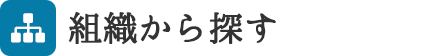
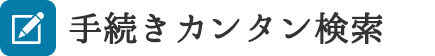
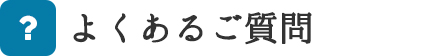
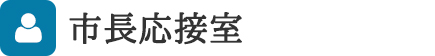

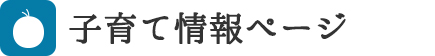
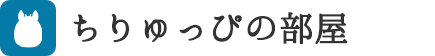
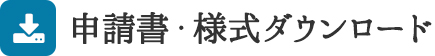

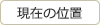

更新日:2024年10月01日