納税の方法(普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収)
個人の市民税・県民税の納税方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つがあり、そのいずれかによって納税することとなります。
普通徴収
事業所得者などの市民税・県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、年4回に分けて納税者本人が直接納税していただきます。
これを
普通徴収
といいます。
なお、普通徴収の際は、便利な口座振替納税をぜひご利用ください。
給与からの特別徴収
給与所得者の市民税・県民税は、特別徴収税額通知書により、市から会社などの給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に、給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納税していただくことになっています。
これを
特別徴収
といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。
なお、給与所得者の納税は、原則として特別徴収の方法によらなければなりません。
年度途中に退職等された場合
毎月の給与から特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降特別徴収ができなくなった残りの市民税・県民税額は、次のような場合の他は、普通徴収の方法によって納税します。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き新しい会社で特別徴収されることを申し出た場合。(各納期限までに、会社の給与担当者を通じて市にお申込みください。)
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額をまとめて最後の月の給料や退職手当などから天引きすることを申し出た場合。
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人のうち、5月31日までに支払われる給与または退職手当等が残額を超える場合(この場合、原則本人の申し出がなくても給与または退職手当等から、残税額がまとめて徴収されます。
公的年金からの特別徴収
地方税法の改正により、65歳以上の方を対象に公的年金等の所得に係る市県民税の特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)が導入されました。
なお、この特別徴収制度は、お支払い方法が変わるだけで新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収の対象となる方
次の1から5までの条件に全て該当する方が対象となります。
- 当該年度の初日(4月1日)時点で65歳以上の方
- 1月1日以降、引き続き知立市内に住所を有する方
- 4月1日現在、公的年金から介護保険料が特別徴収されている方
- 特別徴収の対象となる公的年金の給付額の年額が18万円以上の方
- 前年中に公的年金等を受給されており、当該年度公的年金等の所得に係る市県民税が課税される方
公的年金からの特別徴収の対象となる年金
- 老齢基礎年金・老齢年金・退職年金(老齢又は退職を支給事由とする年金)などが対象となります。
※遺族年金・障害年金は対象ではありません。
公的年金からの特別徴収の対象となる税額
- 公的年金等の所得に係る市県民税
※給与所得など公的年金等以外の所得に係る市県民税は、公的年金からの特別徴収の対象とならないため、別に普通徴収または給与所得に係る特別徴収の方法により納めていただくことになります。
公的年金の所得に係る税額の徴収時期とその方法
※以下の例は年金所得しかない方の場合です。
新たに公的年金から特別徴収される方
10月から、公的年金支給のつど(10月、12月、2月)、年税額の1/6の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。年度の前半(6月、8月)については、年税額の1/4の額を、納税通知書または納付書によって納付していただきます。
| 徴収方法 | 普通徴収 | 公的年金からの特別徴収 | |||
| 徴収時期 | 1期(6月末) | 2期(8月末) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
年税額の6分の1 |
前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方
| 徴収方法 |
公的年金からの特別徴収 |
|||||
| 仮特別徴収 | 特別徴収 | |||||
| 徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | (前年度の年税額×2分の1)÷3 | (前年度の年税額×2分の1)÷3 | (前年度の年税額×2分の1)÷3 | (年税額-仮特別徴収分)÷3 | (年税額-仮特別徴収分)÷3 | (年税額-仮特別徴収分)÷3 |
4月、6月、8月は、前年度の年税額の1/2の額を1/3した税額を公的年金から差し引いて納付(仮特別徴収)していただきます。
10月、12月、2月は、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の1/3の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。
公的年金からの特別徴収税額が変更となる場合
公的年金からの特別徴収は、以下のような事由が発生した場合に中止となります。その際には、市民税・県民税納税通知書を送付しますので、同封の納付書により納めていただくことになります。
○公的年金からの特別徴収が中止となる事由
(1) 公的年金からの特別徴収税額が変更した場合
(2) 他市へ転出した場合
(3) 死亡した場合
(4) その他特別な事由(日本年金機構などの年金支払者から中止依頼があった場合など)
※平成28年10月1日以降からは制度改正により税額変更及び他市への転出となった際でも一定の要件の下、特別徴収が停止されなくなる場合があります。
留意事項
- 公的年金からの特別徴収については、後期高齢者医療保険料・国民健康保険料のように、本人の希望による徴収方法の選択制度はありません。
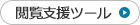








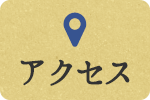
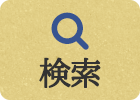
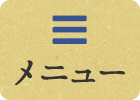

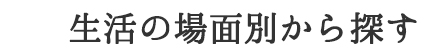








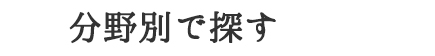
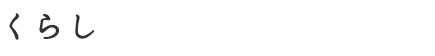


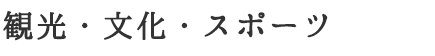


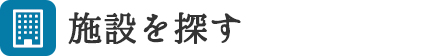
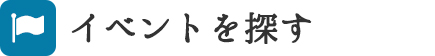
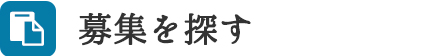
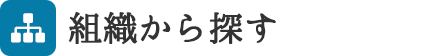
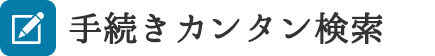
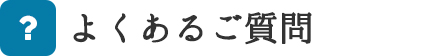
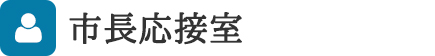

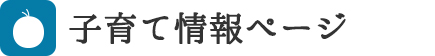
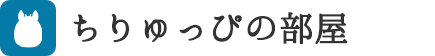
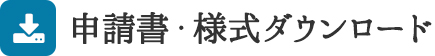

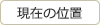

更新日:2023年08月23日