定額減税補足給付金(不足額給付)について【受付終了】
制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
※課税状況の調査等により、発送時期が遅れる可能性があります。ご了承ください。
対象者への通知方法・発送時期等【受付終了】
| 対象者 |
支給口座情報の登録の有る方 |
支給口座情報の登録の無い方 |
| 通知方法 | 支給のお知らせ | 支給確認書(返信封筒付き) |
| 発送時期 | 8月13日より順次発送 | 8月13日より順次発送 |
| 申請方法 |
申請不要 ※口座変更を希望される方、又は受給辞退を希望される方は下記コールセンターまでご連絡ください。 |
10月31日(金曜日)(消印有効)までに返信用封筒又は直接、知立市役所税務課(知立市役所1階4番窓口)へ提出又は確認書に記載されているURLからオンライン申請してください。 |
※令和6年中知立市に転入された方や下記「不足額給付2」に該当する方につきましても、知立市にて給付額の算定・調査を行い、ご案内をお送りする予定ですが、世帯等の状況によっては送付できないことがあります。支給対象にもかかわらず8月中に書類が届かない方は、9月以降に知立市役所税務課市民税係までご連絡ください。
※郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
不足額給付1
対象者
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額(※)及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
(※)国が提供する不足額給付のための「算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計した額
令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
- 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
給付金額
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の方 など
給付金額
原則4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
定額減税について
制度概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税において定額減税を実施することが決定されました。
定額減税の対象者
令和6年度の市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。
非課税の場合や市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。
定額減税額の算出方法
納税義務者の税額控除後の所得割額から以下の金額を特別控除します。(控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。)
- 納税義務者(本人) 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき、1万円
具体例
本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の4人家族の場合の市県民税の定額減税額
1万円(本人) + 3人 × 1万円 = 4万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年分の源泉徴収票等を活用し、令和7年度の市県民税所得割額から1万円を特別控除する予定です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、合計所得金額1,000万円超の人の被扶養配偶者のことです。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。ただし、次のような場合は下記の減税方法とは異なります。
- 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)
- 年度途中に新たに課税される場合
- 税額変更が生じる場合
給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

普通徴収(個人で納付)の場合
令和6年度の市県民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、新たに特別徴収が開始される場合
令和6年度の市県民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除され、控除しきれない部分の金額は、第2期分(8月分)、令和6年10月以降の年金天引き時の税額から順次控除されます。

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、前年から継続して特別徴収される場合
令和6年10月の支給分の年金から、特別控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。

その他注意事項
次の算定基礎となる令和6年度の市県民税所得割額は、定額減税前の市県民税所得割額で計算を行います。
- ふるさと納税の特例控除の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額
定額減税補足給付金(調整給付)【受付終了】
制度概要
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。
(注1)定額減税可能額は次のとおりです。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
市県民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)
(*)国外居住者を除く
(注2)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分市県民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)を基に令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。
支給額
次の(1)及び(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます)
(1)所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)ー令和6年分推計所得税額
((1)が0未満の場合は0 )
(2)市県民税所得割分定額減税可能額(1万円×減税対象人数)ー令和6年度市県民税所得割額
((2)が0未満の場合は0 )
支給対象者
次の(1)~(3)の全てに該当する者
(1)令和6年1月1日現在で知立市内に住所を有する者
(2)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の者
(3)令和6年分推計所得税額または令和6年度分市県民税で定額減税しきれない方
発送時期
令和6年8月13日(火曜日)から順次発送しました。
※土日、郵便物全体の配送量などの状況によっては、発送から1週間程度確認書の到着に時間を要する場合がございます。
発送物
(1)公金受取口座の登録がされていない方へ発送(返送要)
・知立市定額減税補足給付金支給確認書
・返信用封筒
(2)公金受取口座が登録されている方へ発送(返送不要)
・知立市定額減税補足給付金支給のお知らせ
申請方法【受付終了】
・オンライン申請(確認書の二次元コードを読み取り、必要事項を入力して申請)
・郵送(必要事項を記入し、返信用封筒で返送)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
※申請期限までに返送がない場合は、本支給金の支給を辞退したものとみなします。
よくあるご質問
Q1.市県民税の税額変更令和6年分所得税額の確定などにより、給付金額に不足が生じた場合はどうなりますか?
A1.当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。
Q2.令和6年分所得税額の実績が確定し、調整給付金が過大となった場合どのようになりますか?
A2.調整給付金が過大だった場合、返還は求めません。
Q3.この給付金は課税対象ですか?
A3.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき給付金の収入は非課税です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金等に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
・ATM(現金自動払機)の操作を指示すること
・給付のために手数料などの振込を求めること
・申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
・通帳や印鑑を第三者に渡すように指示すること
自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、電子メールや郵便が届いたりした場合、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(定額減税等詐欺注意リーフレット) (PDFファイル: 460.2KB)
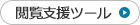








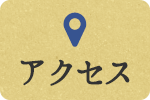
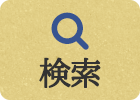
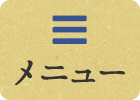

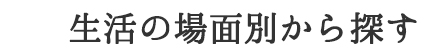








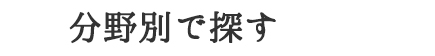
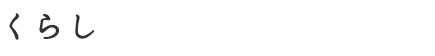


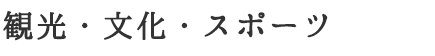


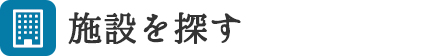
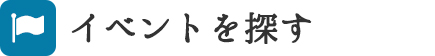
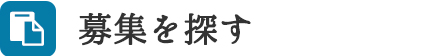
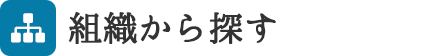
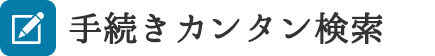
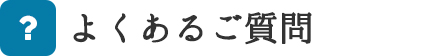
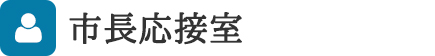

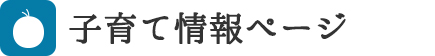
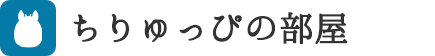
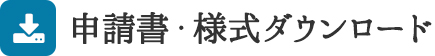

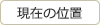

更新日:2025年11月18日