出産育児一時金・葬祭費
出産育児一時金
被保険者が出産した場合、原則として国保から医療機関に50万円(産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は48.8万円)が支給されます。 出産費用が50万円を超えた場合は、差額分を退院時に医療機関にお支払いください。なお、50万円未満の場合は差額分を国保に請求することができます。
出産育児一時金の申請について
直接支払制度を利用する場合、国保医療課への申請は必要ありません。
以下の場合は、申請が必要です。
・直接支払制度を利用しなかった場合(出産費用を全額自己負担した場合)
・出産費用が50万円(もしくは48.8万円)を超えなかった場合
・海外で出産した場合
【申請に必要なもの】
・分娩者の資格確認書類(保険証、マイナ保険証、資格確認書)
・手続きをする人の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、パスポート、通帳、受給者証等)
・世帯主の銀行口座のわかるもの
・出産費用の明細書等
・医療機関から交付された「直接支払制度の利用」にかかる同意書
・医師もしくは助産師の証明書(流産、死産の場合)医師もしくは助産師の証明書(流産、死産の場合)
・(海外での出産の場合)出産証明書の写し(日本語を添付してください)、パスポート
・(世帯主以外の口座への振り込み、もしくは分娩者とは別世帯の人が手続きをする場合)委任状
注意事項
- ただし、6ヶ月以内に社会保険等の被保険者本人として、1年以上加入していた場合は、国保ではなく社会保険等から支給を受けることもできます。
- 妊娠13週(85日)以上であれば死産や流産でも支給されます。
- 直接支払制度を利用しない場合は医療機関での支払後に請求してください。
- 出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。
- 世帯主以外に出産育児一時金を支給する場合は委任状が必要です。
葬祭費のお知らせ
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に5万円が申請により支給されます。ただし、3ヶ月以内に社会保険等の被保険者本人として加入していた場合は、国保からではなく社会保険等から支給を受けることもできます。
申請に必要なもの
資格確認書類(保険証、マイナ保険証、資格確認書)、喪主の銀行口座のわかるもの、
喪主であることがわかるもの(会葬礼状や葬儀の領収書等)
注意事項
- 葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。
- 喪主以外に葬祭費を支給する場合は委任状が必要です。
加入者もしくは加入者がいる世帯の世帯主が亡くなった際の手続き
| 必要な手続き | 持ち物 | 手続き可能な人 |
|---|---|---|
| 保険証等の返納 |
亡くなった方の保険証等 (保険証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証等) |
どなたでも可 |
| 国民健康保険税の還付 |
・相続人代表者名義の金融機関振込先口座のわかるもの ・手続きする人の身分証明書 |
親族または代理人(請求者は相続人代表者様になります) |
| (世帯主が亡くなり、同一世帯に国保加入者がいる場合)保険証等の差し替え |
国保加入者の保険証等 (保険証、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証等) |
同一世帯の方 |
| (口座振替にて国保税を納めていた世帯主が亡くなった場合)口座振替の停止 |
・手続きする人の身分証明書 |
親族または代理人 |
| (新しく世帯主になる方が口座振替にて国保税の納税を希望する場合)口座振替の登録 |
・手続きする人の身分証明書 ・通帳またはキャッシュカード、銀行印 |
親族または代理人 |
| (社会保険加入者が亡くなり、被扶養者が加入できる健康保険がなくなった場合)国民健康保険の加入 |
・社会保険資格喪失連絡票 ・手続きする人の身分証明書 ※資格喪失日から14日以内に国保の加入手続きをしてください。 |
国民健康保険に加入する方もしくはその方と同一世帯の方 |
手続きする人の身分証明書は顔写真付きのもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)であれば1点、顔写真のないもの(資格確認書類、通帳、受給者証等)であれば2点以上必要です。
上記の手続きのほか、必要な手続きがある場合もあります。詳しくは、知立市役所国保医療課国保年金係までお問合せいただくか、「おくやみ窓口」をご利用ください。(「おくやみ窓口」は事前予約制です。)
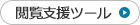








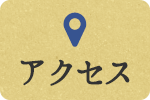
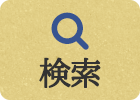
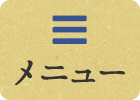

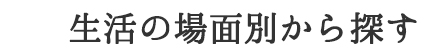








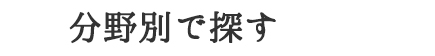
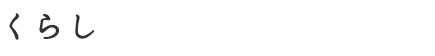


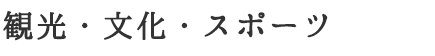


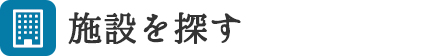
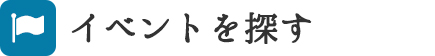
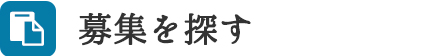
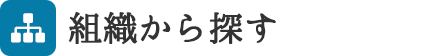
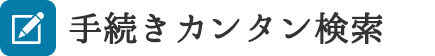
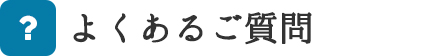
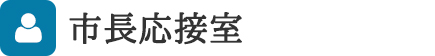

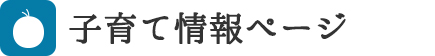
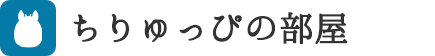
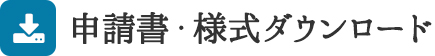

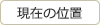

更新日:2023年04月01日