B型肝炎
| 標準的な接種年齢 | 2か月~9か月 |
|---|---|
| 有効期間 | 1歳に達するまで |
| 回数と間隔 |
3回(2回目は1回目から27日以上の間隔をあけて、3回目は1回目から139日以上の間隔をあける。) |
| 通知対象者 | 「こんにちは赤ちゃん訪問」でお知らせ |
| 接種場所 | 個別予防接種医療機関で個別接種 |
病気の説明
B型肝炎ウイルスの感染を受けると、急性肝炎となりそのまま回復する場合もあれば、慢性肝炎となる場合があります。一部劇症肝炎といって、激しい症状から死に至ることもあります。また症状としては明らかにならないままウイルスが肝臓の中に潜み、年月を経て慢性肝炎・肝硬変・肝がんなどになることがあります。ことに年齢が小さいほど急性肝炎の症状は軽いかあるいは症状はあまりはっきりしない一方、ウイルスがそのまま潜んでしまう持続感染の形をとりやすいことが知られています。感染は、肝炎ウイルス(HBs抗原)陽性の母親から生まれた新生児、肝炎ウイルス陽性の血液に直接触れたような場合、肝炎ウイルス陽性者との性的接触などで生じます。過去には保育所での集団感染や家族内感染も報告されています。
B型肝炎ワクチン
B型肝炎ワクチンは、ことに小児の場合は肝炎の予防というより持続肝炎を防ぎ、将来発生するかもしれない慢性肝炎・肝硬変・肝がんの発生を防ごうとすることが最大の目的です。そのため、最も感染リスクが高い肝炎ウイルス陽性の母親から生まれた子どもに出生後できるだけ早く肝炎ワクチンを接種します。しかし、そのタイミングが遅れた場合、ワクチン接種に気づくのが遅かった場合、父親や家族が肝炎ウイルス陽性である場合にも感染リスクはあるので、気づいた時点でなるべく早く接種が勧められます。
なお、わが国で供給されているB型肝炎ワクチンの中には容器のゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれているものがあります。ラテックス過敏症のある被接種者においてはアレルギー反応があらわれる可能性があるためご注意ください。
ワクチンの副反応
10%前後に倦怠感、頭痛、局所の腫脹(はれ)、発赤、疼痛等がみられたと報告がされていますが、新生児・乳児についても問題なく行われています。平成25年4月1日~令和5年9月30日までに医療機関から重篤として報告された例(報告者が重篤と判断するもの)の発生頻度は、0.0008%となっています。
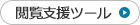








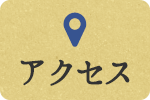
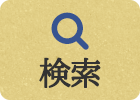
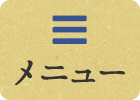

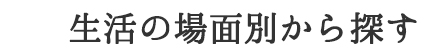








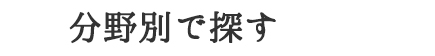
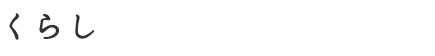


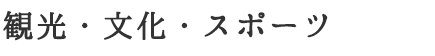


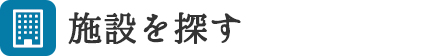
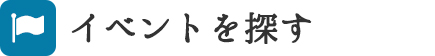
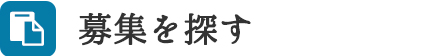
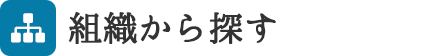
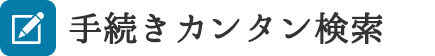
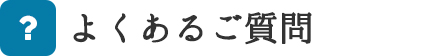
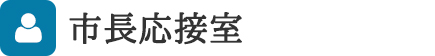

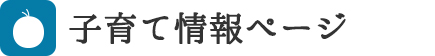
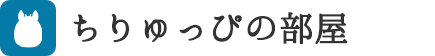
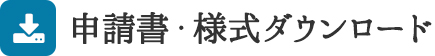

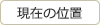

更新日:2025年04月01日