知立まつり
令和7年度知立まつり(間祭り)
知立まつり(間祭り)詳細はこちらから 【知立市観光協会HP】
「知立まつり」とは
知立神社の祭礼である「知立まつり」は、初夏を飾る一大風物詩で、1年おきに本祭と間祭が5月2日、3日に行われます。
祭りの歴史は古く、江戸時代(1653年―「中町祭礼帳」)から続いており、山車の上で山車文楽・からくり人形芝居が上演されるのが特徴です。

本祭り(画像左)
間祭り(画像右)
本祭(ほんまつり)は、5つの町から高さ7メートル、重さ5トンの5台の山車が繰り出されます。神舞と呼ばれる囃子にあわせ、家々の軒を圧するように順行するさまは壮麗そのもの。
また、山車の台上で奉納上演される人形浄瑠璃芝居の「山車文楽」と「からくり」(国の重要無形民俗文化財。かつては山車の上の段でからくりが、下の段で文楽を上演。現在は西町がからくり、山町・中新町・本町・宝町は文楽)は、ともに江戸時代から伝承されている情趣豊かな郷土芸能の粋であります。
間祭(あいまつり)は、5つの町から勇壮華麗な5台の花車が繰り出されます。「山車文楽」と「からくり」はありません。
知立まつり(本祭り)

山車の構造は2層で、車輪は内輪で、松の大木を輪切りにしたものです。形態は知多地方の山車に似ていますが、彫刻に金箔を施し、梶棒が後方だけにあるのが特徴です。
山車(だし)

文楽(3人遣いの人形浄瑠璃芝居)は各地で上演されていますが、山車の上で上演するのは知立だけです。知立では、江戸時代(1747年―「中町祭礼帳」)から始まっており、250年余の歴史があります。現在では、山町・中新町・本町・宝町(平成16年より)の4台の山車で「三番叟」「傾城阿波の鳴門」「壺坂観音霊験記」「神霊矢口の渡し」などを上演しています。
国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産「知立山車文楽」
(国指定重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産)

知立のからくりは、浄瑠璃にあわせて、からくりだけでものがたりを上演する大変珍しいもので、現在は「一の谷合戦」を上演しています。また、知立では、からくり人形を町内の人が工夫して作り、江戸時代(1724年―「中町祭礼帳」)から受け継がれてきました。からくりは、バネやぜんまいで自動的に動くものと、糸を操って動かす方法の2つがあり、知立のからくりは後者に属し、操るのに高度な技術が必要です。
国指定重要無形民俗文化財・ユネスコ無形文化遺産「知立の山車からくり」
(国指定重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産)

知立まつり(間祭り)

会場:知立神社(西町神田地内)他
交通:名鉄知立駅下車徒歩10分
問合せ:知立神社(0566)81-0055・知立市観光協会(0566)83-1111
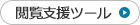








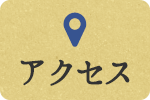
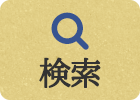
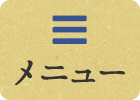

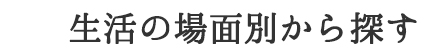








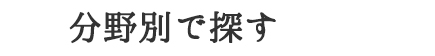
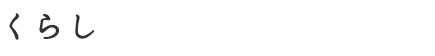


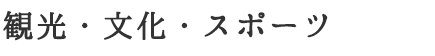


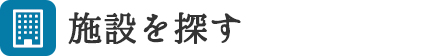
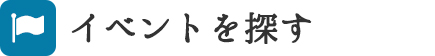
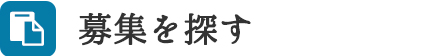
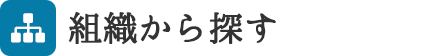
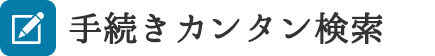
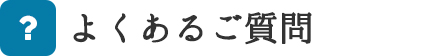
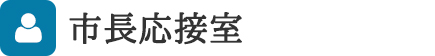

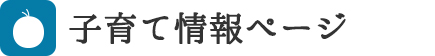
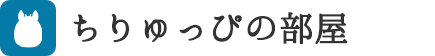
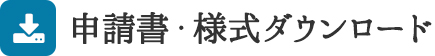

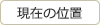

更新日:2025年03月24日