もっと知りたい!史跡八橋かきつばたまつり
このページでは、皆さまに「史跡八橋かきつばたまつり」をもっとお楽しみいただけるよう、周辺の史跡や八橋にゆかりの深い人物などについて紹介しています。
ぜひ観光にお役立てください!

行ってみよう!周辺史跡のご案内
落田中の一松(おちたなかのひとつまつ)
平安の頃、この付近一帯は低地になっていて、逢妻川の乱流の洲だったと言われています。ここには落田中の一松という松があり、かきつばたが咲き乱れていました。 在原業平(ありわらのなりひら)が東国へ下る途中、足をここにとどめてかきつばたを観賞し、都を偲んで「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」という歌を詠んだ、と言われています。
現在は「かきつ姫公園」として整備されています。

業平塚(なりひらづか)
在原業平の供養のために建てられた宝篋印塔で、室町時代のものとされています。
現在の業平塚のある場所は、「八橋伝説地」として愛知県の名勝に指定されています。

根上りの松
根が2メートルほど持ち上がっていることから名づけられ、鎌倉街道の傍らに往時の賑わいを偲ぶように立っています。
松の根本には「鎌倉街道之跡」の碑があり、碑陰には阿仏尼の「十六夜日記」の一節が刻まれています。
「五十三次名所図会」などの浮世絵にも登場します。

在原寺(ざいげんじ)
業平塚を守る人のお堂として創建されたと伝わります。文化2年(1805)に八橋にやって来た方巌売茶翁(ほうがんばいさおう)により再興され、そのときに山号が「紫燕山(しえんざん)」と改められたと言います。
現在は臨済宗妙心寺派に属しており、寺宝として、ご本尊の「十一面観世音菩薩立像」が安置されています。境内には、松堂義玄や種田山頭火など、俳人や歌人の句碑があります。

鎌倉街道
この地域では、中世の東海道を近世の東海道と区別するために鎌倉街道と呼称しました。京都と鎌倉を結んだ街道です。
愛知県内では、知立市八橋町の他、一宮市、あま市、名古屋市、豊田市、豊橋市などに鎌倉街道の伝承が残っています。
池鯉鮒の歴史と自然の散歩みちマップ
ここまでに取り上げた史跡は、池鯉鮒散歩みち協議会が製作した「池鯉鮒の歴史と自然の散歩みちマップ」にも掲載されています。
史跡巡りのお供として、ぜひお役立てください!
無量壽寺(むりょうじゅじ)は、どんなお寺?
無量壽寺(むりょうじゅじ)とは
名勝八橋の中心となる寺で、現在臨済宗妙心寺派に属しています。山号は「八橋山」で、寺号は「無量壽寺」です。
寺伝によれば、慶雲元年(704)の創立と言われています。
文化年間に方巌売茶翁により再興され、かきつばたの庭園も整備されました。
本堂にはご本尊の「聖観世音菩薩像(木造)」が安置されており、在原業平の作と言い伝えられています。
ご本尊の傍には、在原業平の立像も安置されています。

境内案内についてはこちらのページをご覧ください
八橋史跡保存館には何がある?
八橋史跡保存館
八橋のかきつばたや在原業平、また、方巌売茶翁にまつわる数十点の文化財が保存されています。
代表的な展示物として、県指定文化財の「竹製笈(たけせいおい)」、市指定文化財の「売茶翁肖像(ばいさおう しょうぞう)」があります。
また、史跡八橋かきつばたまつり期間中は、尾形光琳作「燕子花図屏風(かきつばたず びょうぶ)」の複製、「八橋蒔絵螺鈿硯箱(やつはし まきえ らでん すずりばこ)」の複製、琉球楽器「長線(ちゃんせん)」の再現品が特別展示されます。
展示品について、もっと知りたい方はこちらのページをご覧ください
八橋史跡保存館の来館案内についてはこちらのページをご覧ください
八橋再興の立役者!方巌売茶翁(ほうがんばいさおう)
方巌売茶翁はどんな人?
方巌売茶翁は、江戸時代後期の宝暦10年(1760)、福岡藩士の三男として福岡に生まれました。
両親や兄弟姉妹が早くに亡くなり、18歳頃に長崎の黄檗宗崇福寺に入りました。
その後、京都へ至り臨済宗妙心寺に入山し修行します。
京都の相国寺の大典禅師(だいてんぜんじ)に師事し、大典禅師を通じて高遊外売茶翁(こうゆうがいばいさおう)の生き方や煎茶について学びました。
無量壽寺とのつながりは?
方巌売茶翁は文化2年(1805)に旅の途中で八橋へとやって来ました。
残念ながら、方巌売茶翁が来た当時、在原業平ゆかりの「在原寺」は荒れ果て、かきつばたも見当たらない状態でした。
それを憂えた方巌売茶翁は在原寺を再興し住職となり、続いて無量壽寺に入寺し、かきつばたの庭園を整備しました。
方巌売茶翁が広めた煎茶
方巌売茶翁の生きた江戸時代後期は、抹茶(茶の湯)は確立されていましたが、煎茶はまだ珍しいものでした。
煎茶をもう一つの茶道として確立し、庶民にも広めたのが高遊外売茶翁です。
高遊外売茶翁は、京都で茶を売る風雅な老人として、文化人など多くの人に知られていました。
方巌売茶翁は、この高遊外売茶翁に強く影響されて、自らも茶笈を背負って茶を売りました。
その煎茶の教えは、今も「賣茶流」として伝わっています。
八橋旧蹟保存会と、八橋のかきつばた再生に向けて
八橋旧蹟保存会は、昭和29年(1954年)に設立され、現在は八橋町の方々を中心として活動しています。
八橋かきつばた園において、かきつばたの保存や育成のため年間を通して庭園の清掃や池の除草作業などを行っているほか、見頃の時期に多くのかきつばたが開花するよう、苗の植付けや施肥、消毒なども行っています。
八橋のかきつばたは、環境等の影響により、残念ながら平成24年頃から一時的に育成不良に陥ってしまいました。
かきつばたの再生に向け、平成29年に愛知県農林水産部や西三河農林水産事務所の協力のもと、「八橋かきつばた再生協議会」が立ち上がりました。
愛知県の指導をうけながら、八橋旧蹟保存会や知立市など、保存・育成に携わるものが一丸となって再生に力を尽くしています。


史跡八橋かきつばたまつりについて
本年度の史跡八橋かきつばたまつりについては、こちらのページをご覧ください。
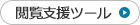








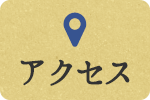
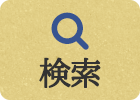
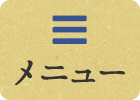

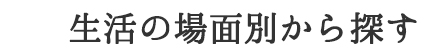








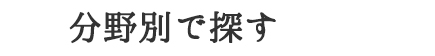
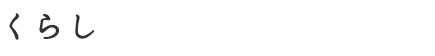


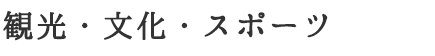


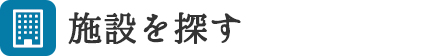
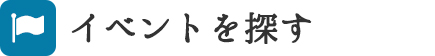
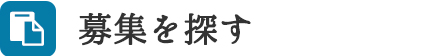
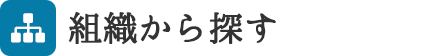
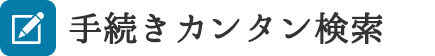
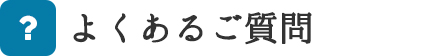
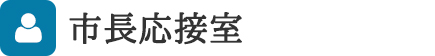

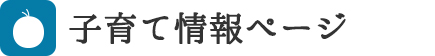
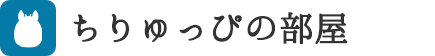
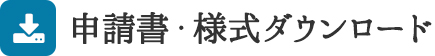

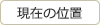

更新日:2023年08月24日